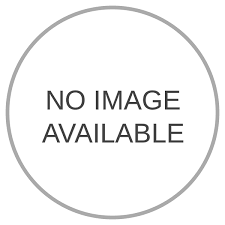2021年02月27日公開
2021年02月27日更新
身分制度「えた・ひにん」とは?意味や現在~多い苗字や地域まとめ【穢多非人】
「えたひにん」とは?江戸時代にえたひにんが暮らした地域、その地域の現在、そして現在の苗字とは?「えたひにん」の苗字、その意味とは?現在も存在するあの職業の職業姓という意味があった。厳しい身分差別を受けた「えたひにん」の生活とは。

目次
- 1「えたひにん」とは?
- 2「えたひにん」の身分制度とは
- 3「えたひにん」の生活とは?生活した地域
- 4「えたひにん」の職業とは?苗字の由来であるのは職業姓という意味があった
- 5「えたひにん」の穢多・非人、その名称の意味とは
- 6「えたひにん」「穢多」と「非人」の違い、その意味
- 7「えたひにん」賤民のなかでもその違いとは?身分がわかれている意味
- 8「非人」には二種類の立場と意味がある
- 9おなじ人間として生まれても「差別」で人生は変わってしまう
- 10「えたひにん」の差別の現在
- 11「えたひにん」穢多の革産業の職業姓、別姓が現在の苗字へ
- 12「えたひにん」その地域とは?現在のあの有名地
- 13「えたひにん」どうして西日本の地域に?
- 14西日本地域だけではない。東京にも当然存在する
- 15地域や苗字をもとに差別するということ
「えたひにん」とは?
えたひにんとは、身分制度のなかの身分の名称、その意味
出典: http://1000ya.isis.ne.jp
「穢多非人(えたひにん)」とはなにか。 地域により、差別的発言という先入観はNG。山間部地域では使われる。が、現在も地域のなかの「集落」の意味として山間部では常用されているので、「差別用語」だという先入観をもつことは懸念すべきであるともいわれる。 出典: http://www.rose.ne.jp 「えたひにん」の身分制度とは士農工商穢多非人(しのうこうしょうえたひにん)とは、江戸時代の身分制度
穢多(えた)出典: https://ja.wikipedia.org 「賤民」の意味賤民:一般の民衆よりも下位に置かれた身分や、その者のこと 非人(ひにん)出典: https://ja.wikipedia.org 「えたひにん」の生活とは?生活した地域「えたひにん」の生活、その差別や制約士農工商穢多非人(しのこうしょうえたひにん)の階級・身分制度が江戸時代に確立されると、人々の生活には貧富の差が顕著に分かれ始めた。 士農工商出典: https://ja.wikipedia.org 「えたひにん」の職業とは?苗字の由来であるのは職業姓という意味があった「えたひにん」の職業は現在も存在する「革産業」苗字はここから決まった穢多(えた)の仕事出典: https://ja.wikipedia.org では穢多非人(えたひにん)のひとびとはどのような仕事をしていたのか。あるいは、どのような仕事が与えられたのだろうか。 穢多(えた)出典: https://ja.wikipedia.org 非人(ひにん)の職業、その身分名称の意味非人(ひにん)の仕事は、溜御用(無宿者のための病監や収容所の管理)・牢屋敷への詰番、囚人送迎・罪人の仕置きの仕事、刑場の管理といった仕事だ。また、乞食を排除する目的で「番非人」や「非人番」として雇われたとされている。 非人(ひにん)の仕事は現在のアングラの意味と同義
部落(同和)問題高村薫著書「レディージョーカー」には、部落問題について書かれている 出典: https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp 明治維新明治維新の「身分解放令」にて穢多非人(えたひにん)の身分は廃止されたが、その後も差別と偏見は残る。 出典: http://www.kodomo.go.jp 「えたひにん」の穢多・非人、その名称の意味とは「えたひにん」(穢多・非人)それぞれの名称の由来と意味餌取(えとり)出典: http://blog.goo.ne.jp 穢多非人(えたひにん)の穢多(えた)の名の由来や語源としては「鷹の餌取(えとり)」という説が専ら謳われるが、根拠ははっきりとされていない。が、江戸時代には屍体処理を行うひとびとに「餌取」という職業があり、これは屍体を鷹の餌として取り処理をする仕事であり、「餌取(えとり)」という言葉と「穢れ」の意味が合わさって「穢多(えた)」という称が使われたとされている。 鷹の餌取(たかのえとり)「えたひにん」「穢多」と「非人」の違い、その意味「穢多」「非人」は姓(苗字)の別称、その意味
「橘逸勢」も、苗字(姓)を改め「非人」へ穢多非人(えたひにん)の非人(ひにん)については、橘逸勢(たちばなのはやなり:平安時代の書家・貴族。空海、嵯峨天皇との三筆とされる)が仁明天皇から謀反人であるとされ包囲されたのち、橘逸勢は重罰を受け姓を「非人」に改めたこと、また農地から逃げ出し人別帖から除かれた人も「非人」と呼ばれ、身分制度から離脱した人を総じて「非人」と名分けしたとされる。 橘逸勢(左)空海、嵯峨天皇に並び三筆の書家とされた 出典: http://www.ten-f.com 伝 橘逸勢筆 伊都内親王願文橘逸勢の書物 出典: http://bunka.nii.ac.jp 江戸時代に確立されたこの身分制度。士農工商は官吏・農民・職人・商人という「四民」とされ「民」の職業を大きく四分別する概念の身分制度となる。 「えたひにん」賤民のなかでもその違いとは?身分がわかれている意味では穢多(えた)と非人(ひにん)の違いとは何か。 穢多が最下位身分の意味とは?仏教に背いた行いをしたから
「非人」には二種類の立場と意味がある
「野非人(のひにん)」とは?「野非人(のひにん)」とは、現代で言われるいわば「路上生活者」「ホームレス」のことである。これは農村部で病などにより年貢を納めることが不可能となった者が江戸へと流れ入った、「無宿者」であった。この者たちを特定の区域で生活させたが、これはのちに「無宿狩り」の引き金となることになる。 「抱非人(かかえひにん)」とは?「抱非人(かかえひにん)」とは、 非人が支払う「銭」は、現在でいう「釈放金」このような罪を犯した「抱非人(かかえひにん)」ならば、家族などの親類縁者が「銭」を支払うことで「平民」に戻ることができた。現代の「釈放金」と同じようなものである。 「穢多」と「非人」最大の違いとは
出典: https://commons.wikimedia.org おなじ人間として生まれても「差別」で人生は変わってしまう「賤民」の生活は厳しいものであった
穢多非人(えたひにん)の位置づけ出典: https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp 「えたひにん」の差別の現在「えたひにん」の現在は?地域や苗字で現在も続いている差別出典: https://matome.naver.jp では「穢多非人(えたひにん)」のひとびとの差別とは現在はどうであるのか。 地域、苗字、現在までと「えたひにん」についての著書は数多い穢多非人(えたひにん)について書かれた書物は多く存在する 出典: http://blog.livedoor.jp 出典: https://www.amazon.co.jp 出典: http://tottoriloop.miya.be 出典: http://koiti-ninngen.cocolog-nifty.com 「えたひにん」穢多の革産業の職業姓、別姓が現在の苗字へ地域に残る部落を記した地図(現在の大阪)穢多非人のひとびとが暮らした集落(部落)。この地図は、現在の大阪とされる。 出典: http://blog.livedoor.jp 苗字を変えて生きるひとびとがいる。苗字から部落差別を受けてしまう現実穢多(えた)牛馬(動物)の毛皮を処理する集団であった。 出典: http://www.kumanolife.com 現代を生きるひとのなかには、祖父母と苗字の漢字に違いがあるというひともいる。 「天狗草紙」「穢多童」が鳥を殺している絵図 出典: http://www.forest-akita.jp 出典: http://blog.goo.ne.jp 「えたひにん」その地域とは?現在のあの有名地では「穢多非人(えたひにん)」の差別的身分制度のなかにいたひとびとは、江戸時代の当時、どの地域で暮らしていたのか。それは西日本地域であり、都道府県で福岡県、広島県、愛媛県には、それぞれ400を越える同和地区が現在も残る。 京都 清水寺古都京都の文化財「清水寺」 出典: http://mendounamasa.info 「えたひにん」どうして西日本の地域に?
京都の仙洞御所出典: http://cocologsatoko.cocolog-nifty.com 現在の京都は歴史が深く残る地域
出典: http://shibayan1954.blog101.fc2.com 西日本地域だけではない。東京にも当然存在する
長州藩の『防長風土注進案』「穢多村」の記載がある 出典: http://blog.goo.ne.jp 関東の地域にも現在も多く存在する「同和地区」現在で確認されている東京の部落の数は、東京都の行政は東京都議会で「東京都内の部落数は234地区」と答弁したことや、『東日本の被差別部落』という書籍には「東京都の被差別部落数は248地区」であると記載されていることなど、東京にも多くの部落が存在することが記録として残っている。東京都のなかでも部落数が多い地域は八王子、青海などが記録されている。 出典: http://kotora888.art-studio.cc 西日本が多くを占める 地域と苗字で「元部落」だと判断するひとも存在する東京のなかでも都心部においては現在は原型を無くし、発展故に部落の跡形も残っていないと言われる。東京の都心部には、地方に比べると高齢の方が生活している世帯が少ないため、東京の中心、都市部で現代を生きている若者たちにとっては近い存在や問題ではないように感じている者が多いとされるのだろうが、高齢の方や歴史的知識に詳しい方、実際に偏見や差別を受けた方…、とかく、なかには苗字と出身地で「元部落」だとわかるというひとも居るようだ。 地域や苗字をもとに差別するということ地域や苗字から部落差別の対象になってしまう現実歴史を振り返ると、差別はつきものなのだと知るわたしたち現代人は「ひとは生まれながら平等であるべきだ」「こんなひどいことをするなんて」と感じたり、あるいは「差別があっても当然のことだ」「身分や階級で生活も仕事も変わるのは仕方ない」などと、おそらく、いろいろな考え方が今日も混在している。権力や思想が上へ上へと昇りつめかたまっていけば、世の中ごとひっくり返るように変化するのは歴史上何度も起こり、現在も現代で実際に起こっている。そうして繰り返していく日々を、わたしたちは生きている。過去の歴史のなかを先祖も生き抜いてきたからこそ、このように代々と「語られてきた」ものが山のようにあり、わたしたちはそれを知り、また考え、何かにつなげ、また「語り継いで」いく。それが大きな流れとして「歴史」というものになるのだろうか。ひとつの歴史を知ることで、ものの見方が少し変わってくるように感じたりもするものだ。 出典: http://blog.goo.ne.jp 部落差別と天皇制は、いまもなお問題視されている 編集部 この記事のライター Cherish編集部 人気の記事人気のあるまとめランキング
新着一覧最近公開されたまとめ
|